前回から、「連結会計」の範囲に突入しました。
今回は連結の中でも基礎的な処理の方法について解説します。
連結の問題の中でも点数に直結する内容も多いのですので、しっかり理解しましょう!
非支配株主持分
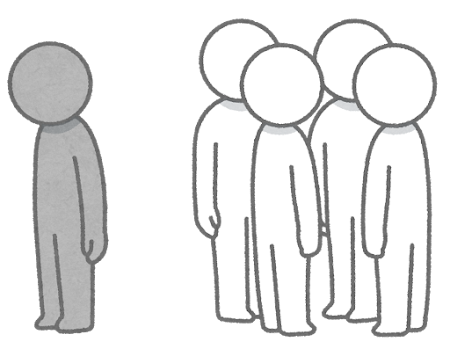
親会社が子会社の発行する株式を100%所有しない場合は、親会社以外の株式所有者が存在することになります。
この所有者のことを「非支配株主」といいます。
この場合、親会社の持分は投資と資本の相殺消去を行い、非支配株主分については「非支配株主持分」として処理されます。
(資 本 金)9,000 (S 社 株 式)9,000
(資本剰余金)1,000 (非支配株主持分)6,000※
(利益剰余金)5,000
※非支配株主持分の求め方:純資産の合計金額に持分比率をかけて求める。
(9,000+1,000+5,000)×(100%-60%【親会社持分】)=6,000
のれん
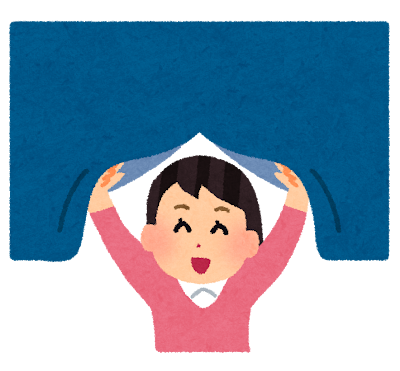
親会社の子会社に対する投資と資本の相殺消去において差額が生じた場合には差額が借方に発生した場合は「のれん」(資産)として処理します。
また、のれんは資産に計上し20年以内において合理的な方法で規則的に償却します。
のれん自体は他企業との競争において時間とともにその価値は減少すると考えられています。
ただし、海外ではこの方法は採られていないようです。
一方、差額が貸方の場合は「負ののれん」として処理し、発生年度において「負ののれん発生益」(収益)として処理します。

簿記2級で「負ののれん」が出題されるのは考えにくいですが、一応解説しときました。
①開始仕訳
(資 本 金)9,000(S 社 株 式)11,000
(資本剰余金)1,000(非支配株主持分)6,000※
(利益剰余金)5,000
(の れ ん)2,000
※(9,000+1,000+5,000)×(100%-60%)=6,000
②のれんの償却
(のれん償却額)200(の れ ん)200
①開始仕訳
(資 本 金)9,000(S 社 株 式)7,000
(資本剰余金)1,000(非支配株主持分)6,000※
(利益剰余金)5,000(負 の の れ ん)2,000
※(9,000+1,000+5,000)×(100%-60%)=6,000
②負ののれんの処理
(負ののれん)2,000(負ののれん発生益)2,000
取得後の利益剰余金の増減と被支配株主持分


連結会計において子会社取得後に増減する子会社の利益の増減額は重要です。

なぜ?

親会社にとって子会社は投資の対象だからです。
子会社の利益は投資の成果と考えられます。

子会社の利益を親会社と非支配株主で山分けするイメージです。
その際行われる仕訳は以下の様になります。
子会社の当期純利益が計上されるとその金額だけ子会社の利益剰余金は増加します。
そのうちの非支配株主持分にかかる金額については、貸方に「非支配持分」へ振り替える必要があります。
借方は、親会社に帰属する当期純利益を調整するために、「非支配株主に帰属する当期純利益」として処理します。

親会社への利益はどうするの?

親会社への利益は合算の段階で計算されています。
そこで、×1年3月31日における連結財務諸表を作成するために必要とされる連結修正仕訳をしなさい。ただし、のれんは発生年度から10年間で償却するものとする。
①開始仕訳
(資 本 金)38,000(S 社 株 式)31,600
(資本剰余金) 2,000(非支配株主持分)20,000 ※1
(利益剰余金)10,000
(の れ ん)1,600 ※2
※1(38,000+2,000+10,000)×(100%-60%)=20,000
※2 差額
②のれんの償却
(のれん償却額)160(のれん)160※3
※3 1,600÷10=160
③当期純利益の振替
(非支配株主に帰属する当期純利益)4,800(非支配株主持分)4,800 ※4
※4 12,000×(100%-60%)=4,800
まとめ
①非支配株主持分
非支配株主持分の求め方:純資産の合計金額に持分比率をかけて求める
②のれん
借方側に発生⇒「のれん」(資産)として処理
貸方側に発生⇒「負ののれんの発生益」(収益)として処理
③取得後の利益剰余金の増減と被支配株主持分
(非支配株主に帰属する当期純利益)××× (被支配株主)×××










コメント