今回の内容は理論的な内容の「会計上の変更・誤謬の訂正」を解説します。
一見簿記には関係なくない?と読み飛ばす方もいらっしゃるかもしれません。
 タカ
タカしかし待ってください!この考え方は計算に直結します。
考え方の基礎を知ることにより応用的な考え方ができるようになります。
この考え方を理解しておくと今後が楽になるので、ぜひともしっかり理解しましょう。
会計上の変更・誤謬の訂正


会計上の変更とは?
会計上の変更とは、①会計方針の変更、②表示方法の変更、③会計上の見積の変更を言います。


この分野は理論的な内容ですが、
特に③の会計上の見積の変更が今後の計算上、重要ですのでここで解説します。
会計方針の変更について
(1)会計方針とは?
会計方針とは財務諸表作成の際にあたって作成した会計処理の原則及び手続きをいいます。


例えば、減価償却の方法を定額法にするか、定率法にするかの選択なんかですね。
(2)会計方針の変更とは?
会計方針の変更とは「従来採用していた一般に公正妥当とみとめられていた会計方針」から「他の一般に公正妥当とみとめられる会計方針に変更」することを言います。
(3)会計方針の変更の分類
2,従来認められていた会計処理の原則及び手続きを任意に選択する余地ががなくなる場合
3,既存の会計基準の廃止、新たな会計基準の設定された場合。
4,上記以外の場合(具体的には、正当な理由により自発的に会計方針の変更を行う場合)


このあたりは将来会計士試験を受けようと思っている方は暗記してください。
そうでない方はふーんでいいと思います。
(4)会計方針の変更にならない場合
1,会計事象等の重要性が増したことによる本来の会計処理の原則及び手続きへの変更


これは会計方針の変更ではなく当然の手続きです。
2,新たな事実の発生に伴う新たな会計処理の原則及び手続きへの変更


これも「変更」ではなく、当然の変更だね。
3,連結財務諸表作成のための基本になる重要な事項のうち、連結または持分法の適用範囲に関する変動


これは会計処理の原則である会計方針とは関係ありません。
(5)会計方針の取り扱い
1,会計方針に関する原則的な取り扱い(遡及適用)
正当な理由により会計方針の変更を行った場合、過年度に遡って財務諸表の作成を行うことになる。
(これを「遡及適用」といいます。)
⇒変更後の会計方針を過年度から適用していたとして財務諸表の作成を行う。


具体的には以下の処理を行います。


????


これはなにを言っているのかといいますと、財務諸表は通常2期間の比較表示になります。
つまり、前期の財務諸表の資産、負債、純資産について会計方針の変更を適用した場合の累積的影響額を適用した財務諸表を作成することになります。
これにより、財務諸表の比較可能性が担保されます。
2,原則的な取り扱いが実務上不可能な場合
以下の様な場合、遡及適用が実務上不可能な場合があります。
b遡及適用にあたって過去における経営者の意図について仮定することについて仮定することが必要な場合
c会計上の見積を必要とする場合、会計事象等が発生した時点の状況に関する情報について、対象となる過去の財務諸表が作成された時点で入手可能であったものとその後判明したものとに客観的に区別することが時の経過により不可能な場合
表示の変更


(1)表示方法とは
表示方法とは財務諸表の作成にあたって採用した表示方法をいい、財務諸表の科目分類、科目配列、報告様式が含まれます。
(2)表示方法の変更
表示方法の変更とは「従来採用していた一般に公正妥当とみとめられていた表示方法」から「他の一般に公正妥当とみとめられる表示方法に変更」することを言います。
②以下の場合を除き継続して適用する必要があります。
b、会計事象等を財務諸表により適切に反映するため表示方法の変更を行う場合
(3)表示方法の変更の区別
①表示方法の変更になるもの
a、損益取引について営業外収益から売上高に区分変更する際に、資産・負債・損益の認識、測定に何ら変更を伴う物でない場合
b、表示の変更は、財務諸表における同一区分内での科目の独立表記、統合あるいは科目名変更及び重要性の増加に伴う表示の変更のほか財務諸表の表示区分をこえた表示の変更も含まれる。
c、キャッシュ・フロー計算書における表示区分を変更した場合や営業活動によるキャッシュフローに関する表示方法を変更した場合は表示方法の変更に該当する。


営業活動によるキャッシュフローに関する表示方法とは間接法を直接法に変更した場合を言いますが、キャッシュフロー計算書については後ほど解説します。
②表示方法の変更にならないもの
b、キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲を変更する場合は会計方針の変更となる。
(4)財務諸表の表示方法の変更を変更した場合の処理
遡及適用処理を行います。
b、実務上不可能な場合:財務諸表の組み換えが実行可能な最も古い期間から新たな表示を適用する。
(5)注記
財務諸表の組替えの内容、財務諸表の組替えを行った理由、組替えられた過去の財務諸表の主な表示項目の金額、原則的な取り扱いが実務上不可能な場合にはその理由を注記する。
会計上の見積りの変更




ここから先が特に重要な内容です。
(1)会計上の見積とは
会計上の見積りとは資産・負債・収益・費用等額について不確実性がある場合において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて、その合理的な金額を算出することをいいます。
(2)会計上の見積りの変更とは
新たに入手可能となった情報にもとづいて、過去に財務諸表を作成する際に行った会計上の見積を変更することをいいます。
(3)会計上の見積りの変更の処理
その影響を当期以降の財務諸表において認識する。
つまり…
・過去に遡って処理しない。


この考え方は今後様々な内容に適用されます。
具体例
①有形固定資産・無形固定資産の減価償却方法の変更の取り扱い
⇒会計上の見積りの変更と同様に将来に向けて会計処理を行う。


ここは会計士の短答式で頻出の内容です。
会計士試験も視野に入れてる方は頭に入れときましょう。
②有形固定資産の耐用年数の見積
b、過去に定めた耐用年数が、その定めた時点で合理的な見積りでなかった場合にはそれ以降の新たな見積りは「過去の誤謬の訂正」として扱います。
過去の誤謬の訂正


(1)誤謬とは?
誤謬とは、意図的であるかにかかわらず財務諸表作成時に入手可能な情報を作成しなかったことによる、、または誤用したことによる誤りをいいます。
具体的には
②事実の見落としやデータ収集または処理上の誤り
③会計方針の適用の誤りまたは表所の方法の誤り
(2)誤謬の処理
遡及処理を行います。
まとめ
会計方針の変更
会計方針の変更の処理
⇒遡及適用を行う
表示期間より前の期間に関する遡及適用による累積的影響は表示する期間のうち、最も古い期間の期首の資産、負債、純資産の額に反映する。
表示の変更
財務諸表の表示方法の変更を変更した場合の処理
⇒遡及適用を行う
b、実務上不可能な場合:財務諸表の組み換えが実行可能な最も古い期間から新たな表示を適用する。
会計上の見積りの変更
具体例
有形固定資産・無形固定資産の減価償却方法の変更の取り扱い
過去の誤謬の訂正⇒遡及処理


つまり見積りの変更以外はすべて遡及適用を行うんだね。

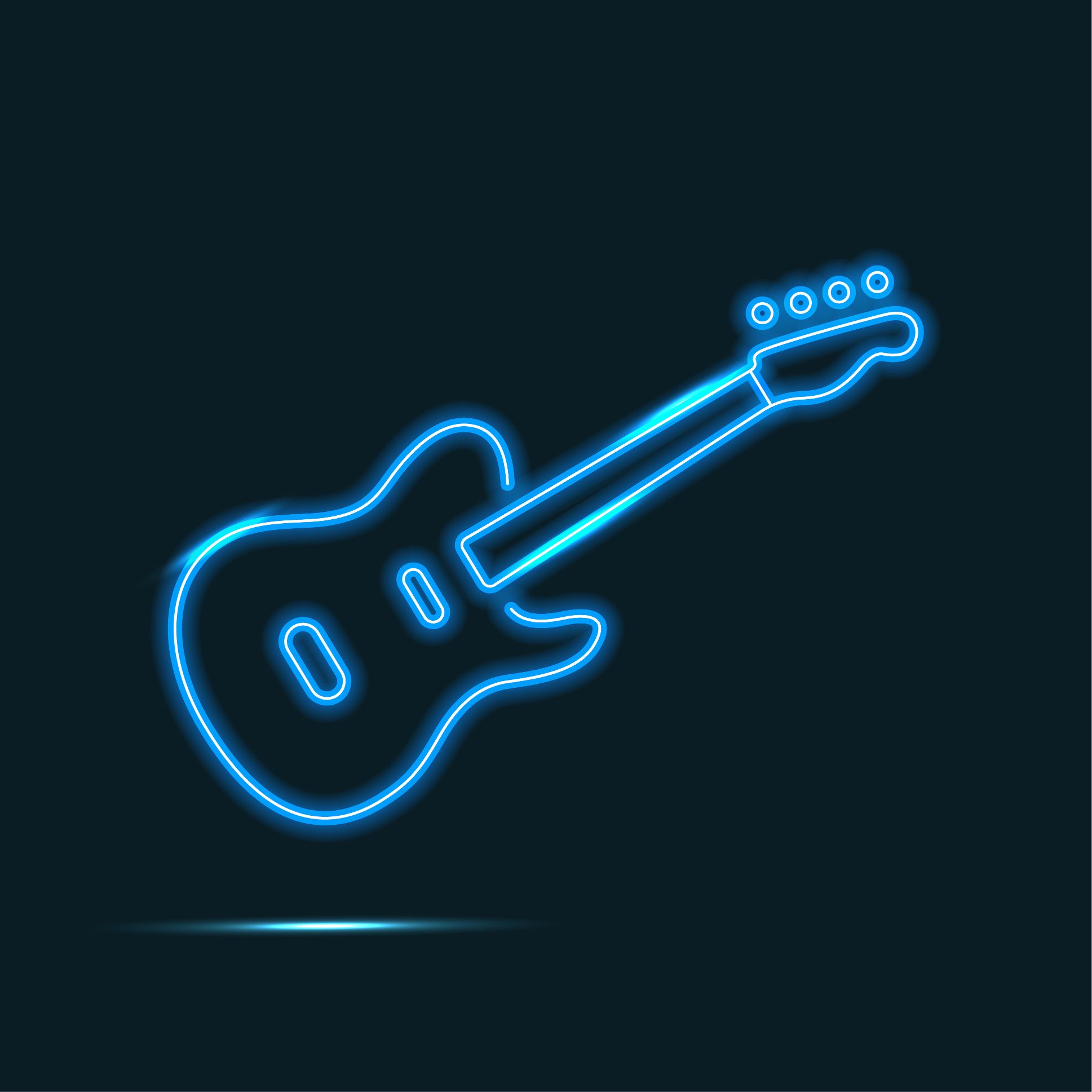








コメント