前回の減損の問題は解けましたでしょうか?

まだの方は下記のページから解いてみてくださいね。
https://bkforworkers.com/4417/
今回の問題はかなり本格的な問題になりますので出題意図を理解したうえで、しっかり復習しましょう。
特に問題3の割引率については解説回で扱っておりませんのでぜひ最後まで読んでくださいね。
- 今回の問題の出題意図
- 問題1:割引計算の理解の確認
問題2:減損損失の按分の理解の確認
問題3:割引率についての解説・確認
問題1
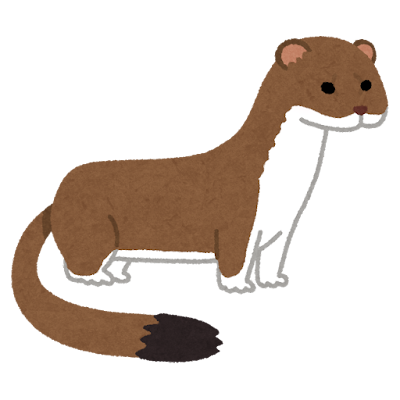
回答
割引前将来キャッシュフロー 181,574
構成資産Bに配分される減損損失 26,951
解説
タイムテーブル
1,割引前将来キャッシュフロー
①1年目から20年目
95,000+3,000+42,000=140,000
②20年目以降
21年目:10,000×0.952=9,520(21年目から1年間の割引計算)
22年目:10,000×0.907=9,070 (22年目から2年間の割引計算)
23年目:9,000×0.864=7,776 (23年目から3年間の割引計算)
24年目:8,000×0.823=6,584 (24年目から4年間の割引計算)
25年目:(7,000+4,000(25年目の正味売却価額))×0.784=8,624 (25年目から5年間の割引計算)
合 計:9,520+9,070+7,776+6,584+8,624=41,574
③割引前将来キャッシュフロー:140,000+41,574=181,574
④減損損失の判定
帳簿価額210,000(注)>割引前将来CF181,574 ⇒ 減損損失を認識する
注:(資産A)150,000+(資産B)60,000=210,000
2,回収可能価額の算定
①使用価値:
100,000(20年目までの将来CFの割引現在価値)+41,574(21年目以降の将来CFの20年目時点の割引現在価値)×0.377(20年目の現価係数)≒115,673

この計算方法が一癖ですね。
どの数字がどの状態なのかしっかり把握しましょう。

20年目のCF×20年目の現価係数で現在価値になりますね。
②正味売却価額:80,000
③回収可能価額:使用価値115,673>正味売却価額80,000⇒回収可能価額115,673(使用価値)
3,減損損失の測定
①帳簿価額の合計:(資産A)150,000+(資産B)60,000=210,000
②減損損失:(帳簿価額)210,000-(回収可能価額)115,673=94,327
4,構成資産Bに配分される減損損失
94,327×60,000(構成資産B)÷210,000(帳簿価額)≒26,951
問題2

回答
資産グループCの帳簿価額:143,695
共用資産の帳簿価額:44,000
解説
1,個々の資産グループの減損損失
①資産グループA
判定
帳簿価額204,000>将来割引前CF187,680⇒認識する
測定
帳簿価額204,000-140,760=63,240
②資産グループB
判定
帳簿価額156,000>将来割引前CF146,640⇒認識する
測定
156,000-107,648=48,352
③資産グループC
判定
帳簿価額150,000<将来割引前CF171,000⇒認識しない
④資産グループD
判定
帳簿価額90,000<将来割引前CF143,020⇒認識しない
⑤共用資産を含むより大きな単位
判定
帳簿価額672,000(注)>将来割引前CF652,000⇒認識する
注:(資産A)204,000+(資産B)156,000+(資産C)150,000+(資産D)90,000+(共用資産)72,000=672,000
測定
帳簿価額672,000-回収可能価額522,320=149,680

皆さんが問題を解く際には1つ1つ丁寧に判定・測定をする必要はありません。
上記の表のようにまとめてやると早く解けますよ。
2,共用資産への減損損失の配分
①減損損失の増加額
149,680-(資産A)63,240-(資産B)48,352=38,088
②共用資産への配分限度額
共用資産の簿価72,000-正味売却価額44,000=28,000⇒よって共用資産へ28,000減損損失が配分される
③他の資産グループへの配分
減損損失の配分超過額
38,088-28,000=10,088
資産グループCへの配分額
10,088×15,000(Cの簿価)÷240,000(対象の資産の簿価の合計)※1=6,305
※1 資産C150,000+資産D90,000=240,000
資産グループCの帳簿価額:150,000-6,305=143,695
共用資産の帳簿価額:72,000-28,000=44,000

共用資産へののれんの配分の限度額は(帳簿価額-正味売却価額)までです。
簿価全額に配分しないように気を付けましょう。
問題3

回答
167
解説
この問題では割引率の選択が問題となっています。
減損損失について使用する割引率については解説していなかったので、の問題を通じて理解してください。
①帳簿価額
取得価額1,000×経過年数2年÷耐用年数5年=500
②割引前将来キャッシュフロー
×4年3月期:200×40%+240×50%+300×10%=230
×5年3月期:50×20%+150×60%+200×20%=140
合計:230+140=370

この場合は各発生し得る確率をかけたキャッシュフローの合計を各年度の割引前将来キャッシュフローと仮定するので注意しましょう。
帳簿価額500>割引前将来キャッシュフロー370⇒減損を認識する
④測定
(1)使用価値の算定に使用される割引率
使用価値の算定に使用される割引率については以下のような規定が存在します。
- ①貨幣の時間価値を反映した税引前の利率
- ②将来キャッシュフローに見積から乖離するリスクを反映していない場合は当該リスクを割引率に反映させる。

貨幣の時間価値を反映した税引前の利率って?

貨幣の割引計算を行う際に用いられる利率のことをいいます。
これには通常、無リスクの国債の利率を用いることが多いです。
※日本の国債が実際、無リスクかどうかの話は別問題です。
つまり、本問では割引前将来キャッシュフローに乖離するリスクは反映されていないため使用する割引率は8%になります。
(2%は無リスク割引率、追加借入利子率は関係ありません。)
問題文にキャッシュフローの見積にリスクを反映させたという趣旨の文章がないことから上記のように判断しましょう。

つまり、上記の将来割引前キャッシュフロー370の見積には乖離するリスクを反映させません。
(2)回収可能価額
使用価値:230÷1.08+140÷1.08^2≒333
正味売却価額:325
使用価値333>正味売却価額325⇒使用価値333
(3)減損損失
帳簿価額500-回収可能価額333=167
チェックポイント
減損損失で使用する割引率
①判定の段階⇒見積りから乖離するリスクは反映させない
②測定の段階⇒見積りから乖離するリスクは反映させる
リスクなし⇒国債等の無リスクの割引率
リスクあり⇒将来キャッシュフロー(税引前)or割引率(税引前)に反映

今回のpdfはこちらからダウンロードできます。




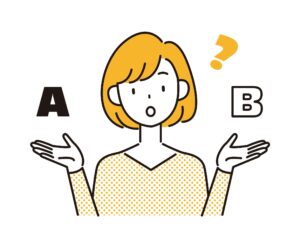





コメント