前回は財務会計はなぜ必要なのか?概念フレームワークとは?といった内容について解説しました。
まだ読んでいない方はぜひ読んでください。
https://bkforworkers.com/4408/
今回は財務会計の情報として扱うにためにはどのような要件を満たす必要があるのか?という
「会計情報の質的特性」について解説します。
この範囲は簿記1級・税理士・会計士で頻出の内容ですので、ぜひ最後まで読んで理解しましょう。
第2章 会計情報の質的特性

投資家が企業価値を評価するためにはどのような財務情報である必要があるのでしょうか?
概フレには以下のように記載されています。
つまり財務会計にとって最も重要な特性(内容)は「意思決定有用性」(投資家が企業の成果を予測するための有用性)です。

なるほど、どんな情報でも使えないと意味がないからね!

投資家の意思決定に使えない情報は財務情報ではないということですね。
さらに以下のように記載されています。
このあたりからややこしくなりますね。
以下の図は上記の解説をする定番の図です。
すこし強引に解説しますと以下のようになります。
チェックポイント
・意思決定有用性=意思決定との関連性+信頼性
・意思決定有用性、意思決定との関連性、信頼性⇐内的整合性+比較可能性

ここから各項目について解説していきます。
意思決定との関連性
意思決定との関連性は以下のように定めれています。
- ①会計情報が将来投資の成果についての予測に関連する内容を含んでおり、企業価値の推定を通じた投資家による意思決定に積極的な影響を与えて貢献することをいう。(情報価値の存在)
- ②会計情報が投資家の意思決定に貢献するか否かは会計情報が情報価値を有していること。また、新たな会計基準については情報価値が不確かな場合が多いが、情報ニーズの存在が新たな情報価値を期待される。(情報ニーズの充足)

う、うーん何言ってんの?

①については投資の成果(利益など)を予測させるような情報を含んでいるかということです。

②について情報に価値がないと意味がないということです。さらに新しい会計基準については情報に価値があるかどうかわからないですが、情報自体にニーズがあるためその情報に価値をもたらすということです。
これらは以下のようにまとまられます。
ここでのポイントは単語とその関係性をしっかり理解することが重要です。
信頼性
信頼性は以下のように定義されています。
さらに信頼性は以下の要素から構成されています。
検証可能性 =測定者の主観に左右されない事実にもとづく財務報告をいう
表現の忠実性=事実と会計上の分類項目との明確な対応関係をいう
つまり以下のようにまとめられますね。

とにかく重要なのは用語をしっかり書けるようにすることです。
内的整合性
内的整合性は以下のように定義されています。

つまり、全体的に矛盾しない考え方のことだね。

全体的に言われればその通りと納得する内容ですが、言葉がやたら難しいですね。
苦手意識を持たずに自分的な言葉で読み替えましょう!
比較可能性
比較可能性は以下のように定義されています。
②会計情報の利用者が期間比較や企業間比較にあたって、同一の事実には同一の会計処理が適用され、異なる事実には異なる会計処理を適用する。

難しいなあ(汗)

これも言葉が難しいだけのパターンですね。
解説すると以下のようになります。
- ①は同一企業でも異なる期間どうしで比較できることまた、同じ期間でも異なる企業どうしで比較できることが必要です。
- ②は同じ経済活動には同じ会計処理を、異なる経済活動には異なる会計処理を適用することが必要ということです。
税理士試験ではおそらく内容を説明させるよりも用語を穴埋めさせる問題が想定できますので、対策はしっかりしましょう。
ポイント

概フレではそれぞれの関係性を以下のように考えています




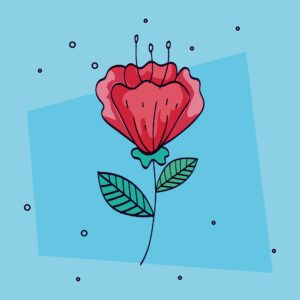

コメント