今回のメインの内容は「サービス業」会計処理について解説します。
 タカ
タカ見た目は難しい感じがしますが、基本的には一般商品売買の延長線上です!
また、現在日本社会はサービス業の割合が非常に多くなっております。
特にGDPに対して約7割も占める状況です。


実務に直結する内容ですので今回の内容はぜひともしっかり押さえましょう。
商品の払出単価の計算




3級の復習は以下のページからお願いします。(先入先出法・移動平均法)


総平均法
5月10日 仕入 100個 @¥1,500
7月20日 仕入 150個 @¥1,200
10月15日 売上 200個 @¥2,000
12月20日 仕入 250個 @¥1,080
2月10日 売上 200個 @¥2,000
平均単価:(100個×¥1,000+150個×¥1,200×250個×¥1080)/(100個+150個+250個)=@¥1,100
売上原価:1,100×400個=¥440,000
役務収益をしっかり理解しよう!


簿記では商品売買を基本とした商売を基本としていますが、上記の通り近年ではサービス業の割合が大きくなっています。
サービス業とは商品の売買でない教育、宅配、飲食といった物理的でない商売のことです。
このような物理的でない提供をサービスといいますが、会計上は「役務」といいます。
サービスの処理
サービスの原価については役務原価(費用)として処理します。
(現 金)300/(役務収益)300
(役務原価)100/(現 金)100
長期にわたる場合のサービス業
サービス業については1年以上の長期にわたる場合が考えられます。


予備校の授業料なんかが該当しますね。
①代金を前受けしたときの処理
サービスの提供に先だって代金を前受した場合「前受金」(負債)で処理します。
(現 金)300/(前 受 金)300
②代金を前払いしたときの処理
いまだ提供していないサービスに掛る費用については「仕掛品」(資産)で処理します。


「仕掛品」については未完成を表す勘定科目で、工業簿記でよく使われる科目です。


「前払金」で処理しないので注意してね。
(仕掛品)100/(現 金)100
また、教育業であれば講師の人件費等を支払ったりしますが、支払った時点では人件費を「給与」等で処理し、後にこの給与について「仕掛品」に振り替えることがあります。
(仕掛品)50/(給 料)50
③決算時の処理
・サービスを提供した割合を前受金から役務収益に振り替えます。
・収益に対応する分の仕掛品から役務原価に振り替えます。
(前 受 金)210/(役務収益)210※1
(役務原価) 70/(仕 掛 品) 70※2
※1 300×0.7=210(前受金の7割を役務収益へ振り替える。)
※2 100×0.7=70 (同じ割合を仕掛品から役務原価へ振り替える。)
(前 受 金)90/(前 受 金)90※
(役務原価)30/(仕 掛 品)30※
※役務提供の残額の前受金、仕掛品の全額を収益、費用計上
繰延資産
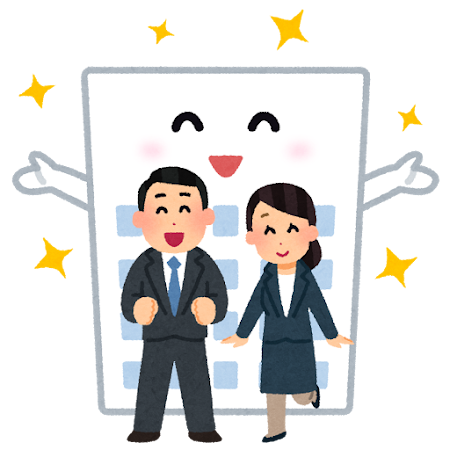
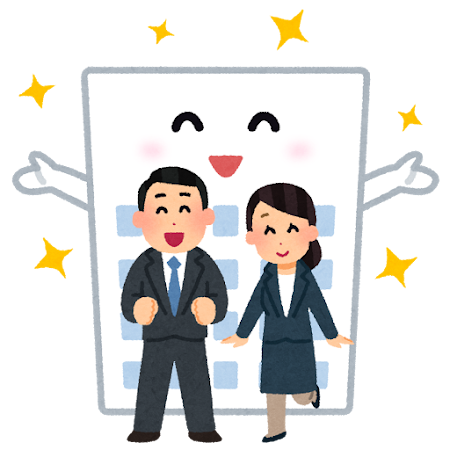
繰延資産とはすでに支払われた代価の支払いが完了し、役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって現れると期待される費用について期間配分するために、経過的に資産として計上するものをいう。
繰延資産の種類
繰延資産には以下の種類があります。
・開業費(会社の成立後営業開始までに支出した開業準備の費用、例えば賃借料人件費等)
・開発費(新技術、新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓等ために支出した費用、但し経常的なものは含まない。)
繰延資産の処理
創立費、開業費、開発費の処理
・償却方法は定額法
・償却費の計上区分:創立費、開業費⇒営業外費用、開発費⇒売上原価、販管費
1級への道
支出の効果が期待されなくなった繰延資産の処理について
支出の効果が期待されなくなった繰延資産の処理についてはその未償却残高を一時に償却
(創立費)900/(現金)900
(創立費償却)180/(創立費)180
まとめ
①払出単価の計算
総平均法
②サービス業の処理
サービスの原価については役務原価(費用)として処理します。
代金を前払いしたとき⇒仕掛品(資産)で処理
・サービスを提供した割合を前受金から役務収益に振り替えます。
・収益に対応する分の仕掛品から役務原価に振り替えます。
③繰延資産
・償却方法は定額法
・償却費の計上区分:創立費、開業費⇒営業外費用、開発費⇒売上原価、販管費
確認問題もあわせてチェックしよう
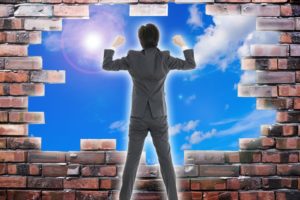
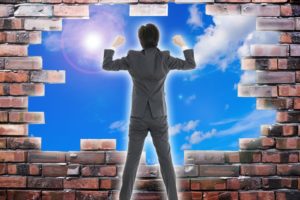










コメント